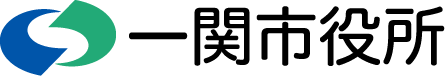生活保護
生活保護の概要
生活保護とは
生活保護とは、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、病気や事故、その他の理由で自分の力では、どうしても生活できない場合に、足りない分を援助し、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう支援することを目的とした制度です。
生活保護の考え方
生活保護は、世帯全員が利用し得る資産、能力などあらゆるものを活用し、それでもなお不足する分を扶助する制度です。
- 能力の活用:働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
- 資産の活用:預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車、利用していない土地などは、原則として売却や解約をして生活費にあててください。
- 扶養義務の履行:親、子、兄弟姉妹などから援助を受けることができる場合には、優先して援助を受けてください。
- 他の制度の活用:年金や手当、自立支援医療など活用できる各種制度を全て利用してください。
生活保護の基準と支給額
保護の決定は、国が定める保護の基準額と世帯の収入額を比較して決定します。
| 最低生活費(保護の基準額) | |||
| 世帯の収入の合計 | 支給される保護費 | ⇒生活保護が適用されるケース | |
| 世帯の収入の合計 | ⇒生活保護が適用されないケース | ||
- 最低生活費について
世帯の年齢、人数、心身の状態、住居の状況などに応じ、国が定める基準により算定されます。 - 世帯の収入について
就労収入(給与、賞与)、年金、手当、農業収入、仕送り、現物援助などの合計額です。
生活保護の種類
生活保護には、次の8つの種類があり、種類ごとに基準額が決められています。世帯の状況により、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
- 生活扶助:食事、衣服、光熱水費など(年齢や世帯人数によって基準額が定められています)
- 住宅扶助:家賃や地代、家屋の修理費用など
- 教育扶助:小中学校の義務教育にかかる学用品、教材代、給食費など
- 医療扶助:病院での治療費や治療材料費、通院のための交通費など
- 介護扶助:介護サービス自己負担分
- 出産扶助:出産、分べんにかかる費用
- 生業扶助:生業のための費用、技能習得費、高等学校等就学費、就職支度費
- 葬祭扶助:葬祭や火葬に係る費用(生活保護を受けている世帯が葬祭を行う場合に限られます)
生活保護の手続き
- 相談:生活保護が受けられるかどうかは、それぞれの世帯の状況により異なりますので、福祉課生活福祉係もしくは各支所市民福祉課までご相談ください。
- 申請:原則として申請手続きが必要です。また、原則として世帯単位で適用されます。
- 調査:担当者が申請世帯を訪問して生活状況や資産などを調査します。また、世帯の収入や預貯金、資産などについて関係機関に対して調査を行います。
- 決定・通知:調査に基づき生活保護受給の可否を決定し、通知書を交付します。保護を開始する場合は支給額(最低生活費基準額から収入を差し引いた額)も通知します。
- 保護費の支給:保護を開始した世帯に、保護費の支給と自立に向けた支援が開始されます。
![]() 生活保護のしおり.pdf [ 370 KB pdfファイル]
生活保護のしおり.pdf [ 370 KB pdfファイル]
生活にお困りの方は、福祉課または各支所市民福祉課までご相談ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日:

 印刷
印刷