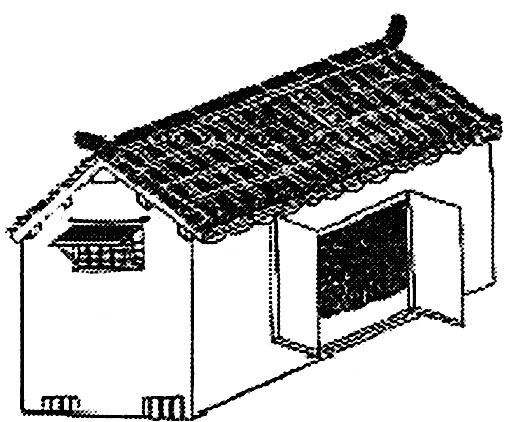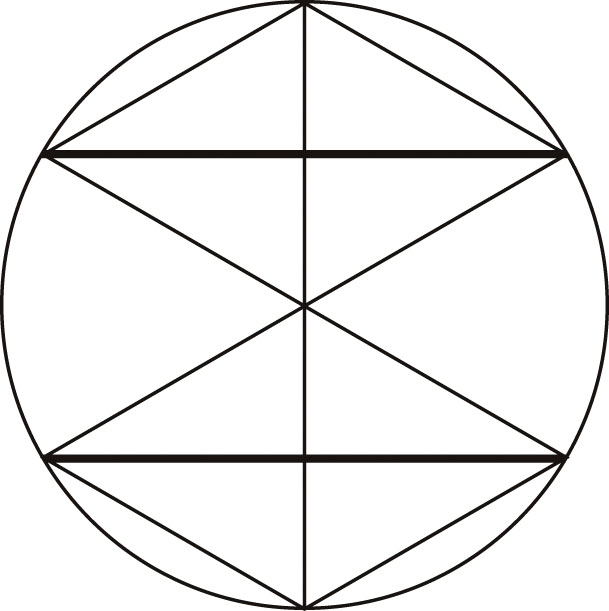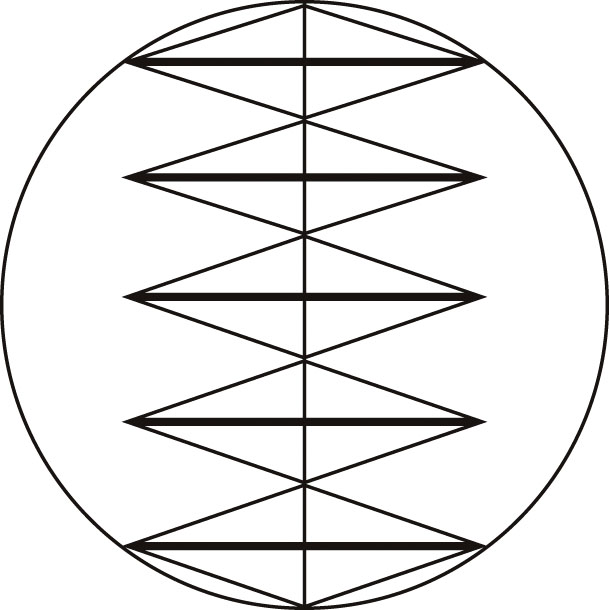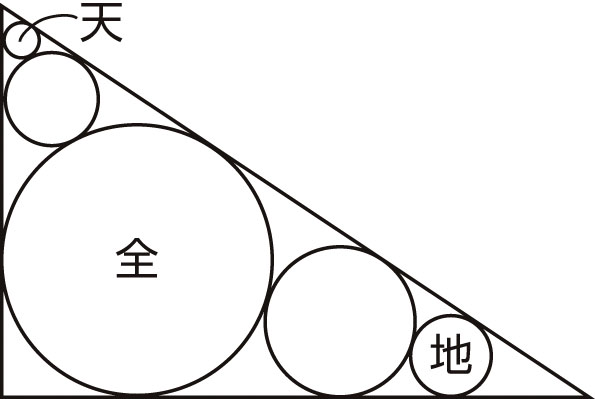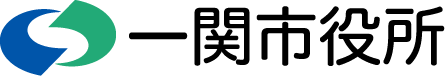博物館だよりvol.34
一関市博物館 第9回 「和算に挑戦」解答募集
江戸時代の数学=和算の問題を現代風にしました。
和算家の知恵に挑戦してみませんか。
応募者全員に解答集を進呈します。
また、優れた解答を表彰します。
【応募方法】
B5判(182×257ミリメートル)程度の用紙に、住所、氏名(匿名不可)、年齢(学生は学校・学年も)、性別、電話番号、問題の解き方と答え、感想などを書き、解答集の送料として80円切手を1枚同封して、左記まで郵送してください。
学校など団体で応募する場合は、あらかじめご相談ください。
コースの選択は自由で、複数でも可です。応募用紙は返却できませんのでご了承ください。
受付期限
平成23年1月20日(木)当日消印有効
あて先・問い合わせ先
〒021‐0101一関市厳美町字沖野々215
一関市博物館「和算に挑戦」係 電話0191-29-3180
※表彰式は23年2月27日(日)13:30から行います。
※正解の発表は同日からホームページ上で、また解答集の発送は3月下旬の予定です。
初級(小・中学生向き)
文化12(1815)年に出版された『算法点竄指南』の問題です。
米をたくわえ蔵があります。
蔵の中から、初日に1石を出します。
次の日に3石、また次の日に7石、その次の日に11石、その次の日に15石を出す、というように米を出していくと、30日で蔵は空になりました。
はじめに入っていた米は何石でしょうか。
※石は、米を量る単位(1石=10斗=100升)
中級(中学・高校生向き)
明治34(1901)年に観福寺(一関市)に奉納された算額の問題です。
図のように、二つの合同なひし形が互いに接して、円に内接しています。円の直径を10cmとするとき、ひし形の長い方の対角線の長さを求めなさい。(1)
同様に、ひし形が五つの場合について求めなさい。(2)
上級(高校生以上)
一関の和算家千葉胤秀が編集した『算法新書』(文政13(1830)年刊行)にある問題です。
図のように5つの円が互いに接して、直角三角形に内接しています。
天円の直径が6.04cm、地円の直径が12.08cmのとき、全円の直径を求めなさい。
一関市博物館案内
テーマ展3 あかり
燭台、あんどん、ちょうちん、ガス灯などの照明器具を「菅原清蔵コレクション」を中心に展示します。■日時…23年1月8日(土)~2月27日(日)
■展示説明会…(1)1月16日(日)11時~12時(2)2月13日(日)11時~12時
いわての博物館交流セミナー2
花巻人形の世界
花巻人形の特徴や歴史、エピソードなどについての講演会です。
■日時…23年1月22日(土)13時30分~15時
■講師…酒井宗孝さん(花巻市博物館上席副主幹兼学芸係長)
■定員…36人
はくぶつかんこどもくらぶ 和紙を染めてみよう
■日時…23年1月9日(日)10時~15時の間随時(所要時間約1時間)
■対象…小学生以上(小学生は保護者同伴)
■定員…事前申し込みは不要ですが、先着50人まで
■参加料…50円
■持ち物…なし。汚れてもいい服装でおいでください。
資料整理のため休館します。
■期間…12月7日(火)~16日(木)
■休館期間中の問い合わせ先…厳美公民館 電話0191-29-2205

 印刷
印刷