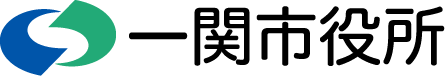文化財探訪/博物館案内
室根神社祭のマツリバ行事~室根~
北上山地の南端、市の東部に広がる緩やかな丘陵地にそびえる室根山。その8合目にある室根神社は、本宮、新宮の2社があります。
本宮は養老2(718)年、鎮守府将軍大野東人が、当時霊威天下第一とされていた紀州婁郡本宮村(現在の和歌山県田辺市本宮町)の熊野神をこの地に勧請(じょう)。
蝦夷との戦いで苦戦したことから、神の加護を頼ろうとしたものです。
熊野神の分霊は、和歌山県から船で5カ月間もかかって現在の宮城県気仙沼市唐桑町に到着。東人は白馬17騎の諸郷主を招集して神輿を迎えました。
勅使から天皇の勅書を受けた後、神主にどの地に祭るかの神意を伺ったところ、室根山とお告げがあったため、室根山の8合目に室根神社が建立されました。
その日が養老2年の旧暦9月19日で、元年が閏年でその翌年の勧請であったことから、その古例を守って閏年の翌年の旧暦9月19日を大祭としています。
新宮は、正和2(1313)年9月、陸奥の守護職葛西清信が紀州牟婁郡新宮村(現在の和歌山県新宮市)から熊野神宮の神霊を勧請。奥七郡の鎮守として祭ったものです。大祭は、本宮勧請の様子を再現したもの。
荒馬17騎、袰先陣(曲ろくの花と大名行列)、袰祭まつり(山車6台)、舞姫による舞が豪華絢爛に行われ、ほぼ当時の様式のまま継承されています。
大祭のメーンとなる3日目朝の「マツリバ行事」は、室根神社から出発し、室根町折壁地内にある祭場まで本宮・新宮両宮神輿を陸尺で担ぎ、先着争いをしながら宮に安着させるという荒祭り。
東北名代荒祭りといわれるゆえんとなっています。
神社の歴史と由緒を現代まで継承し、貴重であると評価されている大祭。
室根神社祭のうち「マツリバ行事」が、昭和56年の県の文化財指定を経て、昭和60年には国の重要無形民俗文化財となりました。
地域での特色ある壮大な祭りとして、現在も継承されています。
一関市博物館案内 電話0191-29-3180 ホームページ
企画展 佐藤紫煙―幻の花鳥画―新潟・大正時代の豪商別邸に残る板戸絵―
一関に生まれた日本画家、佐藤紫煙(明治16年~昭和14年)の代表作を紹介しています。
10月半ばに作品の多くを展示替えしました。
■会期…11月7日(日曜日)まで
あなたも刀鍛冶修業
フイゴや金敷、金づちなど刀鍛冶の道具を使って、五寸釘からペーパーナイフを作ります。
■日時…11月3日(水曜日)(祝)13時~16時
■講師…早坂政義さん(刀匠)
■定員…小学5年生以上、一般20人
■参加料…200円
館長講座 伊達政宗の手紙
政宗の手紙を読み、その人となりや魅力を実感していただきます。■日時…11月7日(日曜日)13時30分~15時30分
■講師…大石直正館長
東北学院大学中世史研究会
■日時…11月13日(土曜日)13時30分~16時30分
■テーマ…中世の宗教史(仮題)
■発表者…「磐井郡の板碑」(当館副館長畠山篤雄)、「奥州葛西氏領における寺社と信仰(仙台市博物館・佐々木徹さん)、「松島の板碑」(東北学院大学・七海雅人さん)
※事前申し込み必要なし

 印刷
印刷